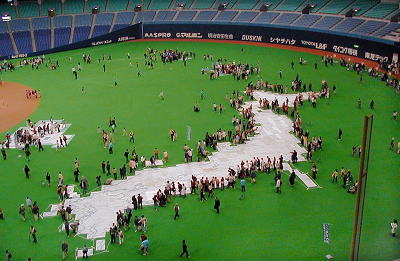2015年のクリスマスも静かに終わりました。クリスマスソングってたくさんあるけど、自分の心に残り、これを聴くとグッとくるものを書き留めてみます。
まずは定番から。
サイレント・イブ(辛島美登里)
1990年11月発売。ドラマ「クリスマス・イブ」主題歌。最初はカラオケトラックなしのCDシングルでの発売だったが、1年後にカラオケも入れて発売され、2年連続でクリスマス時期にチャートインしたとのこと。いやー、いい曲です、ほんと。
次はちょいレアな曲。
かりそめのスウィング(甲斐バンド)1975年
甲斐バンドのクリスマスソングっていうと「安奈」って人がアラフィフ世代でも大半だろうけど、俺にはやはりこの曲ですね。甲斐バンド3枚目のシングル。ちなみに1枚目は「バス通り」(売れなかった)、2枚目は大ヒットした「裏切りの街角」。二匹目のドジョウは狙わないということで全く毛色の違う曲としてリリースされたこの曲。やはり一般受けはしなかったようで、前曲が最高週間7位だったのにこれは44位。でもいい曲なんです!そしてそして、この曲のB面があの名曲「ポップコーンをほおばって」。さすがにリアルタイムでは聴いてない自分としては、この時代にシングルEPレコードを買って、このAB面両面を堪能した人を心から嫉妬してしまいます。
次はこれ。Someday Somewhere (チューリップ)1979年
いわゆるチューリップ第1期、上田さん吉田さんが脱退する前の最後のアルバムタイトルの曲です。チューリップはその後新メンバーで彼らの最大のヒット曲「虹とスニーカーの頃」を出したのですが、コアなファンにはこの曲、このアルバムが大好きな人が多いようです。
�次は博多の昭和(照和)のバンドが二つ続いたので、女性のを。
ロッヂで待つクリスマス(松任谷由実)1978年
この曲はユーミンのアルバム「流線形’80」の一曲目。「’80」ですが発売は1978年の冬。80年代を先取りしたアルバムだったと思います。このアルバムはほんと全部いい曲で、ユーミンも後年のライブでも大体このアルバムからいつも2−3曲を歌っていたと言われております。サーフ天国スキー天国みたいな能天気?な曲にはない、スキー場での微妙な青春時代の男女の気持ちを詩も曲も表現していたように(勝手に)感じます。リンク先のYoutube画像は、あえてユーミンご自身が登場するものより、スキー場の良さげな光景のものにしてしまいました。
そして、クリスマスソングといえばやはりこれだよ!ってのが、
雪にかいたLove Letter(菊池桃子) 1984年
いや、これですよね、やっぱり!! ってあんまり共感得られなさそうですが。。。山下達郎よりWham!より、高校時代のこの曲に自分はシビれました。だって、ただ失恋するとか片思いするとかそんな次元じゃなくて、好きな男の子への想いを、「あなたがいつも通るレンガの石畳、雪の上に、せつない想いだけを、指で書いておくの、もし消えても、泣かない」、、、、ですよ。。
当時はなかった言葉ですがもう萌えまくりでした。
でも個人的には残念なことに作詞は秋元康。フトマキさんです。。。結局この方の財布を厚くしていたと思うとやや残念です。
あの頃は誰が作詞家とか考えずに、桃子ちゃんだけを見つめて聴いていたからただただ感動してたんですけどね。。。。。。それにしても菊池桃子さんは今(2015年)も変わらず素敵です。
昭和が続いたので、平成の歌からももう少し。
『LAT.43°N 〜forty-three degrees north latitude〜』Dreams Come True (1989年)
これって初出は80年代だったんですね。でも、90年代初頭に流行った気がします。実はクリスマスソングって訳でもないんだけど、ホワイトイルミネーションとか、冬の光景が描かれているのと、この北緯43度という言葉に込められた札幌と東京の遠距離恋愛の感覚に当時心を打たれました。
ドリカムのクリスマスソングは他にも色々あるけど、自分が一番クリスマスを感じるのはやはりこれですね。
最後に。
Appears 浜崎あゆみ (1999年)
この歌もそんなにクリスマスって感じでもないかもしれないけど、このPVのあゆは本当に素敵で、カラオケでもよく入っているので、ついつい無理に原Keyで唄いたくなってしまうのが男心というものですな。
とりとめもなく書いてたら5曲のはずが7曲になってしまいましたが、どれもこれも自分の中では鉄板のクリスマスソングです。まあ、冷静に考えるとどの曲も、なんか失恋したり片思いだったり、いわゆるクリぼっちな歌ばかりで、己が非リア充なクリスマスばかり過ごしてきたを吐露しているようですが、それもまた人生ってことで。
でもそればかりでは寂しいかも、ということで最後は明るめな曲で。
wonderful christmastime (Paul McCartony) 1980
これも好きですねー。なんかしみじみしますわ。
この8曲全部カラオケで熱唱できる人とは、初対面で親友になれそうです(笑)
*2016年12月23日追記
Paulの曲を挙げましたけど、やはりJohnもいいですねー。
やはりこの二人は永遠のヒーローです。
みなさまの心に残るクリスマスソングもぜひ聞かせてください!